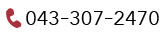新築
信頼性の高い防水層を設置するため、防水施工の前に以下の項目について条件が満たされていることをご確認ください。
①地下の強度が十分であること。
1,現場打ちコンクリートは設計基準強度を満たしていること。
2,防水層に悪影響を及ぼさないように配筋上の配慮や調合設計上の工夫、ならびに打設後の養生等の施工管理に注意することでひび割れの発生を少なくし、分散させる。
3,コンクリート打設後の降雨等で強度が著しく低下している場合は、ハツリ撒去の上コンクリートを打ち直す等の処置にて強度を復旧させる。
②地下の乾燥が十分であること。
1,目視にて表面が白く乾燥していることを確認する。
一般的に普通コンクリートで夏季3週間・冬季4週間程度の乾燥養生期間を目安とするが、地下構成(デッキプレートなどの片面乾燥や吸水性の高い地下など)や天候によって大きく左右されるため、防水層の施工に先立ち以下のような方法で十分に乾燥していることを確認する。
(A)高周波静電容量式水分計を使用した測定。
(B)不透湿シートで床下地表面を履い周囲をガーテープ等張付けで密封状態として、翌日に内面の結露水の有無を確認する。
③表面が平滑であること。
1,平場面はきんゴテ押えで平滑とする。
2,浮き・表面緑離・レイタンス等の脆弱部および鉄筋・番線等の突起物は除去する。
3,豆坂・気泡・あばた・目違い・段差・砂筋等の表面不具合に対する処置を除去する。
4,立上りも平場と同様に平滑とし、凹凸や不具合も平場と同様の処置を施す。
5,ポリマーセメントモルタルを使用する場合は、プライマーの塗布やウレタン塗膜の硬化収縮による破壊・緑離んい耐え得るよう、高い接着強度と耐溶剤性を有する材料(「ダブルテックスNEO」「Dワン・カチオン」または「台ラックスNEO」)をしようする。
④できるだけ速やかに排水させるための処置を施すこと。
1,水勾配は1/100以上とする。
2,ルーフドレーンや排水落し口等はスラブ面より低くし、周囲の水はけを良くしながら堅固に設置する。
3,ドレンはアスファルト防水用またはシート防水用のツバが幅広タイプのものを使用し、塗かけ幅を100㎜以上確保する。
4,ドレンの排水能力は将来の改修工事を見据えて余裕を持たせた設定が望ましい。またドレン以外にもオーバーフロー管を設置し、ここから雨水が落ちてくることで使用者にドレンの目詰り等の排水機能の低下を知らせる措置が望まれる。
⑤地下表面がよく清掃されていること。
1,プライマーや接着剤の接着性を阻害させ、また防水層を劣化させるように塵埃・油脂類・鉄錆等は除去する。
⑥防水層に支障があるひび割れ・打断ぎに適切な処置が施されていること。
1,防水層に支障が無いひび割れ(概ね1.0㎜未満)にはウレタン塗膜防水材またはウレタンシーリング材の擦り込みを施す。但し通気暖衝シートを張る場合は、この限りではない。
2,防水層に支障があるひび割れ(概ね1.0㎜以上)や打継ぎにはUカット後ウレタンシーリング材を充慎するか補強布の増し張り、あるいは両方の処置を施す。但し通気暖衝シートを張る場合は、この限りでは無い。
3,誘発目地・化粧目地には予めウレタンシーリング材を充填しておき、補強布の増し張りを施す。但し通気暖衝シートを張る場合は、この限りでは無い。
⑦入隅および出隅が適切に処理されていること。
1,入隅および立上りの入隅は通りよく、直角とする。また出隅および立上りの出隅は通りよく、R面または45度/W=5㎜以上(メーカー推奨値15~30㎜程度)の面取りを施す。
⑧設備基礎関連で適切な雨仕舞いができること。
1、コンクリート基礎は原則「躯体一体型」とし、防水層の上に載せることは極力避ける。とくに総重量の大きい設備の場合はこれを遵守する。
2,総重量および容積が大きい大型設備のコンクリート基礎は、将来の改修工事を見据えて再塗布が容易となるような作業空間(H450㎜程度以上、推奨600㎜程度以上)を確保することが望ましい。
3,表面は平滑とし、不具合部には適切な処置を施す。また天端は雨水が滞留せず、速やかに排水されるように水平ではなく角度を付けることが望ましい。なお入隅および出隅については⑦と同様とする。
4,アンカー類は原則「先打ち」とし、周囲に幅・深さ10㎜程度の「盗み」をとっておく。また防水層の巻き上げ(天端よりH=15㎜以上)を確保する。
5,基礎ブロックの下やCチャンU(リップ溝形銅)・H銅などと防水層が取り合う部分には防振ゴム(t=5㎜/先端から10㎜以上の余剰分を確保)を設置する。
⑨金物関連の取合いで適切な雨仕舞いができること。
1,H型銅や角形銅管を垂直に設置する場合はベースプレートで完全に固定し、ボトルにはキャップとウレタンシーリング材充填を施す。
2,丸カン・手摺支柱足元等は周囲に幅・深さ10㎜程度の「盗み」をとって、予めシーリング材を充填しておく。また防水層んお巻上げ(H=15㎜以上)を確保す。
3,ウレタン塗膜防水が掛かる部分は目荒し研磨(サンドペーパー#100程度またはサンダー掛け)を行い、その後脱脂処理を施す。とくに「溶融亜鉛メッキ」等、十分な接着力を得られない可能性がある金属下地の場合は入念に行う。
⑩配管および配線が防水施工に支障が無いこと。
1,防水層上での配管および配線の設置は防水施工の後とするか、または施工に支障が無い階段での工事とする。また将来の改修工事を見据えて、再塗布が容易となるような措置(高さの確保、または吊上げが可能な形状と荷重)をとることが望ましい。
2,防水層を貫通する配管や配線は可能な限り避けること.止むを得ず設置する場合は防水施工に支障が無い位置とし、スリーブを使用してウレタン塗膜防水層100㎜以上(推奨値)の補強塗を施す。またグラつきが無いように完全に固定する。
⑪PCa下地およびALC下地の場合の注意点は、以下の通りとする。
1,水勾配は躯体でとり、部材は固定を十分に行いジョイントに生じるムーブメントを可能な限り抑えること。
2,接合部に大きなムーブメントが予測される場合は、絶縁シートをはるか補強布の増し張りを施す。
2,表面はポリマーセントモルタルでひら滑に仕上げる。その際使用する材料は③-5,と同様のものとする。
株式会社AKOOでも信頼できる防水を行っております。
質問、お問い合わせのある方はこちらへ